「mama!milk / Duologue」へご寄稿いただきました。

いちばん好きなのは暗黒映画で、
若いころのベルモンドが頬をそいだように痩せていて、
ひっそりと黙りこくって拳銃をいじっている、
そんなどうでもいいような一篇・・・、
できればジョゼ・ジョヴァンニの
原作か脚本であれば文句ないんだけれど・・・。
mama!milkをはじめて聴いたとき、
すぐに思い浮かべたのはモノクロの暗黒映画で、
路地の奥で音楽を聴くような遠いパトスに攫われて、
熱いものがこみ上げてうろたえた。
暗黒映画というのは、つまりは狭い界隈(ミリュー)の
ひっそりとした暮らしに注がれたまなざしのことで、
ドンパチがあったり隠語でまくしたてたりするけれど、
そこにあるのはコトバを奪われた人々の情愛の交わし合い、
海の中のように黙りこくった世界なのだ。
だから、映像にふさわしい音楽といったら、
手回しオルゴールやバンドネオンといった
雑味がたっぷりとある楽器の奏でるものが最上で、
mama!milkの生駒祐子さんのアコーディオンは
シシリアの工房でつくられたものだと聞いて、
やっぱりそういう血が流れているのかとうなずいた。
「ちっぽけな土地にひっそりと息づいているものほど愛おしい。
逆に愛しいものほど狭いところで
物音ひとつ立てずに生きている。」(ジョゼ・ジョヴァンニ)
おちぶれたものを励ますように、
これでもかと歓待してやまないmama!milk、
暑熱のたそがれに吹く恩寵の風、
涸いた大地にふりそそぐにわか雨だ。
佐伯誠
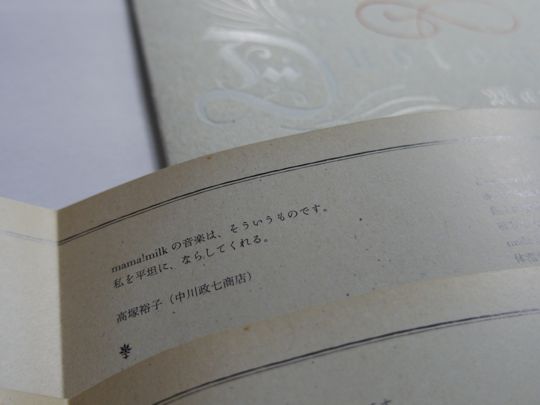
基本、無音が好きだ。ということに、気がついた。
家族と離れ、一人の時間と向き合うのは、
持ってきたのは、洋服と本当によく聴くCD数枚だけ。
この際だからと、TVも買っていない。
自分の為の道具を揃える。
7年間、生活道具の店をやっていたので、
改めて新鮮な作業である。
そっけないくらい狙っていない、
ちょっと不便そうなものが好みだ。
自分なりの居心地を作れる余白があるからいい。
そういうものを見つけるのは、案外むずかしい。
よく、没頭するクセがある。
頑なにストイックというわけではないので、
外野の音や映像があればあるで、はまって困る。
mama!milk の音楽は、
不思議と流していると時に聞こえなくなる。
つまり心地よく自分の中に入っていけるということ。
仕事が変わり、この歳になっても
日々新しい色々な思いにぶつかる。
下を向いてしまう気持ちの時には一緒に暗く、
前を向けそうな時には一緒にそんな兆しにむかってくれる。
程よい距離にいて、私を自由にさせてくれて、
いて欲しい時にはすっと寄り添ってくれる
理想の恋人のようでもあるし、
使い心地のよい道具のようでもある。
本当に大切なものや新しいものは、多くはいらない。
淡々と日々を暮らしていきたい。
毎日くりかえし聴く
mama!milk の音楽は、そういうものです。
私を平坦に、ならしてくれる。
高塚裕子(中川政七商店)
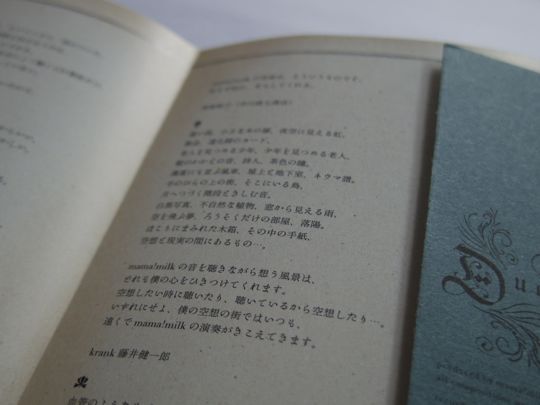
遠い国、小さな木の扉、夜空に見える虹、
教会、道化師のカード。
老人を見つめる少年、少年を見つめる老人、
靴のかかとの音、詩人、茶色の瞳。
幾重にも並ぶ風車、屋上と地下室、ネウマ譜。
手のひらの上の街、そこにいる鳥、
月へつづく階段ときしむ音。
白黒写真、不自然な植物、窓から見える雨、
空を飛ぶ夢、ろうそくだけの部屋、落陽。
ほこりにまみれた木箱、その中の手紙、
空想と現実の間にあるもの・・・。
mama!milkの音を聴きながら想う風景は、
どれも僕の心をひきつけてくれます。
空想したい時に聴いたり、聴いているから空想したり・・・。
いずれにせよ、僕の空想の街ではいつも、
遠くでmama!milkの演奏がきこえてきます。
krank 藤井健一郎
http://www.krank-marcello.com/

血管のようなリボンで綴じられたmama!milkの新譜は
アコーディオンとコントラバスの二人きり。
生み出されるその音は、豊かで鮮烈。
そして攻撃的で澄んでいる。
fragrance of notes、Parade、nudeと
様々な編成遍歴はこの為だったのかと、
数々の演奏、様々な楽器の響き、異国の空気まで、
吸収し取り込んできたのだと思った。
nude以降、mama!milkの演奏を聴く度に、
体温の上昇、血の香り、
身体の中から揺さぶられるような感覚でわくわくしていた。
静かにひっそりと、力強く、冷たく冴える高揚感。
Duologueは、この美しい音楽は、戦いの音楽だ。
そしてやはり戦いは、まずは一人でするものだ。
自分(達)の世界のために、まずは一人で戦うのだ。
今の世の中を、良い風に思っていない人は多いだろうし、
私もそう思っている。
だけど、世の中と自分の世界は「=」ではない。
「今現在」はいつも混沌としていて、
目につきやすいところには、醜いものがいっぱいで
それは、戦いを途方もないものに感じさせ、
私を寂しく不安にさせるけど
だから、今現在、美しいものは存在する。
と、はっきりと感じることができるのは、
私にはとても心強く、大げさでなく生きる希望だ。
しかもこの、耳から入って反射的に、理屈抜きに、
身体で感じる喜びは。
もちろんmama!milkは私や誰かの為に戦っているのではなく、
手を差し伸べてくれるものでもない。
勝手に少し救われて、まだイケル、だろうという気持ちにさせてくれるだけ。
それがどれだけ大事かは、例えようもなく、
そしてやっぱり、自分は自分で、戦わないといけないのでしょう。
争いではない戦いを、途方もなく、終わりもなく、
時には孤独に、強く、美しく、優雅に。
そういうのをロマンティックと言うのだろうと思う。
バイオレンスの同居するロマンティック、
人間にはそういうのが、必要だと私は思っている。
そんなmama!milkに、敬意を表して。
stompdesign 南 知子
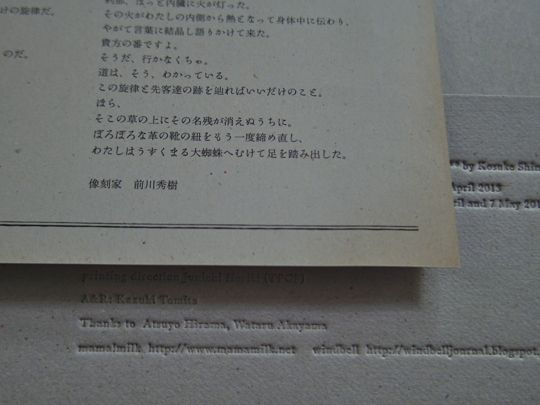
「デュオローグ、という一幕に寄せて」
森を抜けた。
ぱっと開けた視界に見渡す限り波立つ海が広がっていた。
茜色の残照に映える、草の海だった。
わたしは立ち止り、乱れた息をゆっくり整える。
ここまで追っ手が来ることはないだろう。
いや、あるいはまだ・・・。
切れ切れになったスカートの裾をたくし上げ、
傷だらけで血のにじむ脛や粗末な皮靴をそっと撫でたとき、
とたんに膝の力が抜けてその場にへたり込んでしまった。
わたしは泥のようになった身体を草の波打ち際に委ね、
静かに横たわった。
そしていつしかそのまま深く深く眠りに落ちていった。
そのままずっと時間が過ぎてしまったのだろう、
いや、本当はほんの半刻程だったのだろうか。
白河夜船の波間、聞きなれない異国風の楽器の音色が
わたしを緩やかな傾斜の覚醒へと導いた。
しっとりと、身体中の毛穴や細胞の中にまで夜がしみ込んで来ていた。
でも夜にしてはやけに明るい。
ああ、あれ。
夜空に張り付いていたのは水銀色の月だった。
すっかり凪いだ草の海と、わたしの後ろに迫る黒い森に、
平等にぞっとするほど冷たい光の粒子は降り注いでいた。
周囲を見渡す。静かに数呼吸。追っ手らしき気配はなかった。
わたしは胸をなでおろした。
すっかりと覚醒した頭で漸く大きな異変に気がついた。
目覚めたわたしは、重厚なテーブルの前に座っていたのだ。
十フィート以上もあろうかという長い樫のテーブルには、
やはり手の込んだスピンドルバックの樫の椅子が居並んでいた。
ざっと見ただけでも十数脚はある。
わたしはそのひとつに腰掛け、大テーブルに突っ伏して眠っていたのだ。
たった一人で。
一体いつから?
残りの椅子は空席だったが、それぞれの席の前のテーブルの上には、
水銀の照り返す鈍い光を凝縮したような、肉の厚いグラスが置かれていた。
空っぽのものもあれば、透明な液体でなみなみと満たされたものもある。
わたしにどうしろと・・・。
わたしはひとつ小さいため息をつきながら、
目の前に置かれたグラスを手に取った。
わたしの目の前のグラスは、満たされていた。
鼻に近付けてみる。薬酒?アニスにグーズベリー。
トネリコにヤドリギの実の香りも混ざっているかな。他は何だろう。
知っている香りと未知の不思議な香。
精緻に織りこまれた紋様のような、複雑な香を嗅ぎ分けているうち、
香りの糸のすき間から、またあの楽器の音が滑りこんできた。
無論液体は音を奏でない。
音は、この草の海の沖から・・・。
ああ、あそこから。
いつの間にあんなものが・・・。
草の海の沖に小山のように盛り上がる真っ黒な影があった。
長い脚を折り畳みうずくまる巨大な蜘蛛のように見えた。
折りたたんだ長い脚の膝は全て夜空を貫くほど高く、
それぞれの先端にひるがえる黒い旗を
緩やかな風がもてあそんでいた。
ゆるりゆらりと。
サーカスの大天幕だった。
楽器の音はそこから風に乗って響いて来るのだった。
遠いけれども不思議と今ははっきりと聞きとれる。
コントラバスと・・・アコーディオンだろうか?
二つの異なる音色。それがシンプルに響き合うだけの旋律だ。
けれども耳を傾けるうち、
その響き合いがわたしの中にさまざまな場面を
ありありと立ち上がらせてはまたすっと消えてゆくのだ。
異国の香辛料の市場の喧騒。
小さな私の手を握るのは母だろうか。
荒れる海がざっくりと陸地を切り取った白い断崖。
頬に海風が突き刺さる。
苔に半ば覆われた石壁の表面を梟の影が掠めて飛ぶ。
鍵爪に携えるのは誰かの文。
男たちの葉巻の煙と粗野な笑い声。
アブサン酒のとろりと溶けた丸い水面。
そして、祭りの日のようにたくさんの人々が
無言で早足で行き交う、都会の鉄道の駅。
わたし自身の記憶と他人の記憶が
ごちゃ混ぜになっているようだ。
殊更に主張を押し付けることのない、
淡々と奏でられる曲の数々は、だからこそ、
微細な粒子の液体のように、心の襞に難なく滑り込み、
巧みに記憶に作用する。
出会ったことすらない誰かの、いつか見た一場面を、
なり変りこっそり覗き見るような、
奇妙な感覚をわたしにもたらすのだった。
幾人もの人間の人生の幻燈。
あの大天幕の中では今、
一体どんなことが演じられているのだろう。
何者がこの多彩な音色を奏でているのか。いつしかすっかり
あの大蜘蛛に魅せられているわたしがいた。
わたしはようやく手に持ったグラスの液体を一口含んだ。
とろりと月の光が喉を通りぬけた。
刹那、ぽっと内臓に火が灯った。
その火がわたしの内側から熱となって身体中に伝わり、
やがて言葉に結晶し語りかけて来た。
貴方の番ですよ。
そうだ、行かなくちゃ。
道は、そう、わかっている。
この旋律と先客達の跡を辿ればいいだけのこと。
ほら、
そこの草の上にその名残が消えぬうちに。
ぼろぼろな革の靴の紐をもう一度締め直し、
わたしはうずくまる大蜘蛛へむけて足を踏み出した。